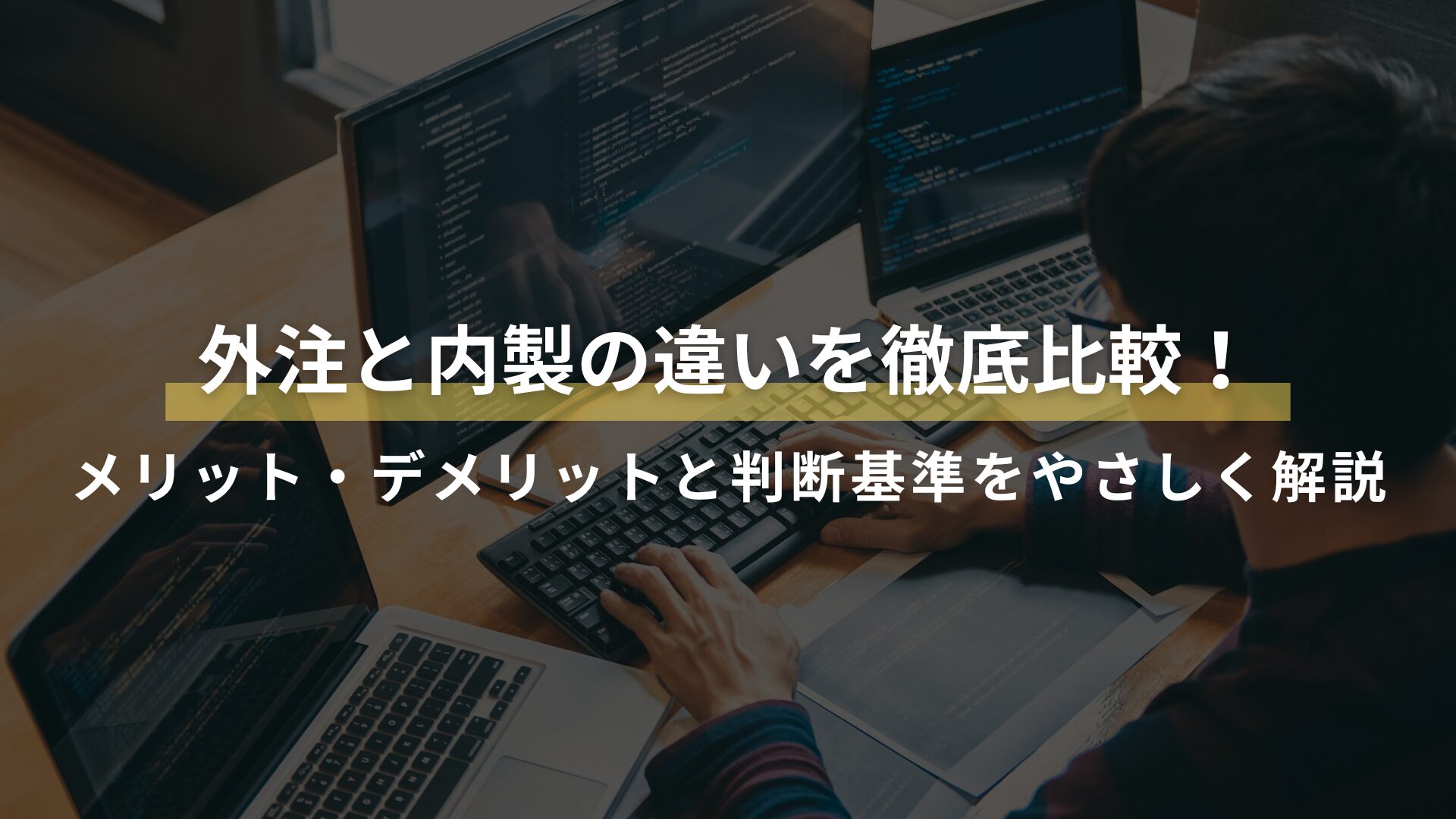「外注にすべきか、内製にすべきか迷っている」
「コストだけで判断していいのか不安になる」
そんな悩みを抱える方は少なくありません。ビジネスを進めるうえで、業務を外注するのか、社内で内製化するのかは大きな経営判断のひとつです。
どちらにもメリットとデメリットがあり、正しい基準を知らないと「コストが膨らむ」「品質が安定しない」といったリスクにつながることも。
本記事では、外注と内製の違いを徹底比較し、判断のポイントをわかりやすく解説していきます。
『運用を始める前のチェックリスト』2大特典無料配布中
外注と内製とは?基本の意味をわかりやすく解説

ビジネスを進めるうえで欠かせない「外注」と「内製」。言葉は知っていても、実際には混同されやすく、判断に迷うことが多いテーマです。
外注ってなに?
外注とは、自社で行うべき業務を外部の専門家や企業に依頼することを指します。
たとえば、広告デザインを制作会社に依頼したり、システム開発をIT企業に任せたりするケースが代表的です。
自社では対応が難しい分野やリソースが不足している部分を補う手段として活用されます。
内製ってなに?
内製とは、外部に依頼せずに自社の人材や設備を用いて業務を進めることを意味します。
社員が自社サイトを更新したり、社内チームが動画や資料を制作したりするような取り組みが典型的です。時間や労力はかかりますが、社内の力を育てながら進めていける点が特徴です。
よくある誤解や混同しやすいポイント
外注と内製は対立する概念に見えますが、実際には誤解されやすい点がいくつかあります。誤った理解のまま判断すると、コストや品質に影響することもあるため注意が必要です。
「外注=高コスト、内製=低コスト」ではない
外注の方が短期的に安く済む場合もあり、逆に内製が高くつくケースもあります。
「外注すると品質が落ちる」わけではない
専門業者に依頼すれば、むしろ高い品質を確保できることも多いです。
「内製=すべて自分たちでやる」ではない
内製を基本としつつ、一部を外注する「ハイブリッド型」も効果的です。
外注を選ぶメリットとデメリット

外注は「自社で対応しきれない部分を補える手段」として多くの企業で利用されています。しかし、利便性が高い一方で注意すべき点もあります。ここでは、代表的なメリットとデメリットを整理します。
メリット①|専門スキルをすぐに使える
外注先はその分野の専門家であり、自社に存在しないスキルや最新知識を短期間で活用することができます。
高度なプログラミングやデザイン、広告運用といった業務を即戦力として導入できるため、社内で人材を育成する時間やコストを削減することが可能です。
特に短期集中型のプロジェクトや、期限の厳しい案件において有効な手段となります。
メリット②|社員の負担を減らせる
業務を抱え込みすぎると社員が疲弊し、本来の業務に集中できなくなりますが、外注を活用することで社内リソースを効率的に使うことができます。
繰り返し発生する業務を外部に任せれば、社員は戦略的な業務に注力でき、長時間労働や離職のリスクを抑えることにもつながります。
さらに繁忙期や急な業務増加にも柔軟に対応できるため、組織全体の安定した稼働を支える手段となります。
メリット③|コストが見えやすい
外注は契約ベースで費用が決まるため、コストが明確で管理しやすいという特徴があります。
必要なときに必要な分だけ利用できるため、設備投資や人材育成に比べて初期費用を抑えやすい点も大きな利点です。
さらに複数の外注先を比較することで、価格や条件を最適化しやすく、予算計画を立てやすい点も魅力といえます。
デメリット①|ノウハウが社内にたまりにくい
外注に依存すると、業務遂行に必要な知識や技術が自社に蓄積されず、ノウハウが残らないという問題が生じます。
契約の終了や担当者の変更によって情報が途切れてしまい、自社で同じ業務を再現することが難しくなる場合があります。
その結果、中長期的には独自性や競争力を高めにくくなり、組織の成長力を損なう可能性があります。
デメリット②|相手のスケジュールに左右される
外注は外部の人材を活用するため、業務の進行は必ず相手の状況に左右されるという特徴があります。
繁忙期には納期が延びるリスクがあり、修正依頼が遅れると全体のスケジュールに影響が及ぶことも少なくありません。
さらに契約条件によっては追加費用や調整コストが発生する場合もあり、想定外の負担につながることがあります。
内製を選ぶメリットとデメリット
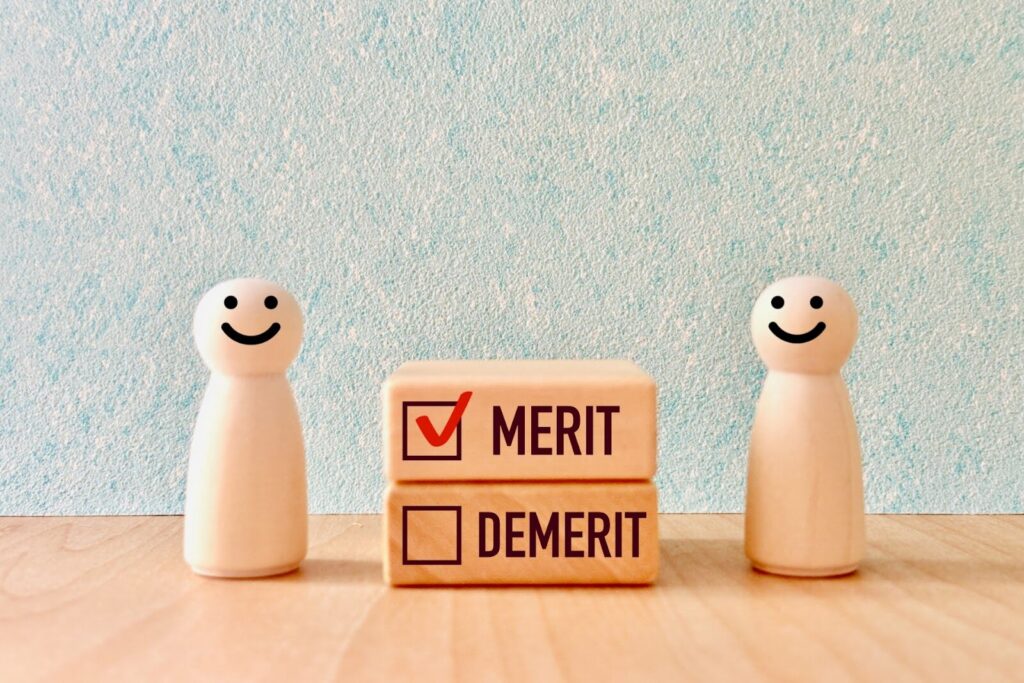
内製は「自社で業務を完結させる」方法であり、長期的に企業の力を強化する手段でもあります。しかし、実行するには人材や時間の確保といった課題も伴います。ここではメリットとデメリットを整理します。
メリット①|社内にノウハウが残る
業務を自社で行うことで、日々の経験や知識が組織内に蓄積されノウハウとして残っていきます。
プロジェクトの過程で得られた知見を再利用することで、将来的に同じような業務をより効率的に遂行できるようになります。
外部に依存する必要がなくなり、自社ならではの独自の強みを構築できる点が大きな利点です。
メリット②|柔軟に変更や改善ができる
内製は社内リソースで完結するため、方針の変更や改善をスピーディに行えるのが大きな特徴です。
修正や改善の指示を即座に反映できるほか、プロジェクトの進行中であっても柔軟に方向転換することが可能です。
市場や顧客の変化にも素早く対応できるため、継続的な改善が求められる業務に適しています。
メリット③|社員のスキルアップにつながる
業務を内製化する過程では、社員が新しい知識や技術を習得しながら成長していくことができます。
その成長は企業全体の競争力を高める力となり、継続的な人材育成を通じて組織の基盤を強化していきます。
さらに社員のモチベーションや主体性の向上にもつながり、長期的に見れば組織の底力を押し上げる効果を発揮します。
デメリット①|採用や教育に時間とコストがかかる
内製化を進めるには、まず適切な人材を採用し、育成していくことが欠かせません。
専門的なスキルを持つ人材を確保するにはコストがかかり、さらに教育や研修のために時間と費用を割く必要があります。
加えて人材が定着しない場合には、それまでの投資が無駄になるリスクもあり、慎重な取り組みが求められます。
デメリット②|担当者に依存してしまうリスクがある
特定の社員に業務が集中すると、知識やスキルが一部に偏り、組織全体としてのリスクが高まります。
担当者が退職や異動をした場合に業務が滞る可能性があり、属人化が進むことで再現性や継続性が失われやすくなります。
さらに業務量が増えると個人の負担が過大になりやすく、結果的に効率やモチベーションの低下を招く恐れがあります。
外注と内製の判断基準と向き不向き
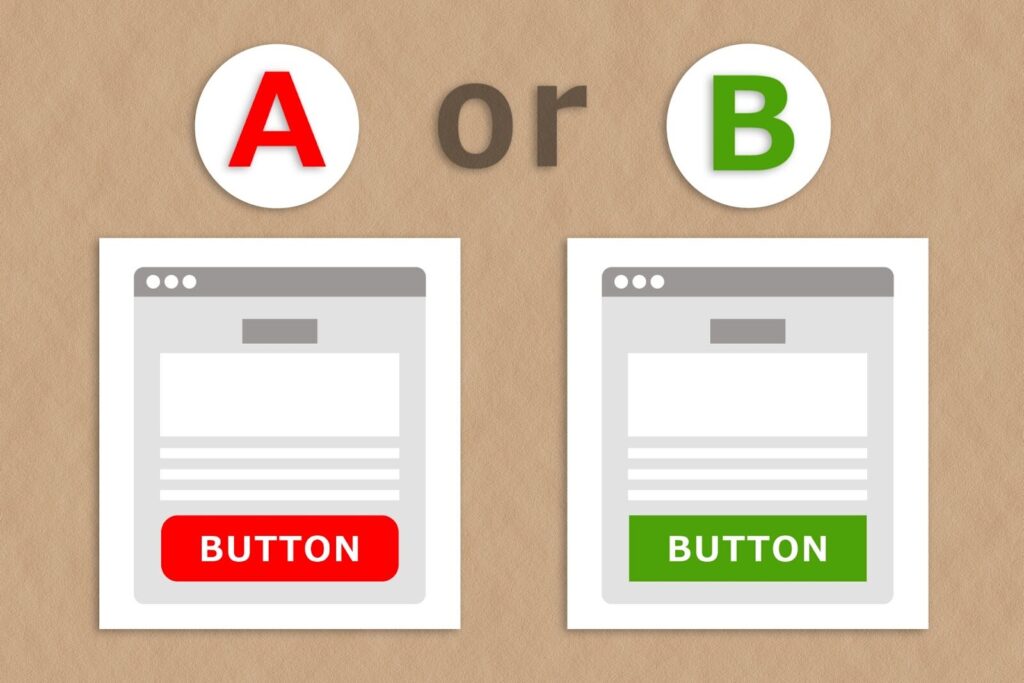
外注と内製はどちらが優れているかという絶対的な答えはありません。重要なのは、自社の状況や目的に応じて適切に選択することです。ここでは、判断の基準となる代表的な4つのポイントを解説します。
判断基準となるポイント
① コストは短期と長期でどう違うか
一度きりのプロジェクトや短期的に成果を求める業務であれば、外部の力を活用する方が初期投資を抑えやすく、コストも明確に管理できます。
逆に、長期的に繰り返し発生する業務であれば、社内で人材を育成し仕組みを整えることで、時間の経過とともにコストを回収しやすくなります。
短期的なコスト削減を優先するのか、長期的な効率化を重視するのかによって選択は変わります。
② スピード感をどこまで重視するか
納期が迫っている場合や即戦力が必要な場合は、外部のリソースを使うことでスピーディに対応できます。
一方で、プロジェクトの途中で細かな修正や改善を繰り返すような業務は、社内で完結させる方が柔軟に対応しやすいといえます。
スピードを最優先するのか、それとも柔軟性を重視するのかが判断の分かれ目です。
③ 品質や専門性の深さは必要か
高度な専門知識や最新技術を求める業務であれば、外部の専門家を活用することで高品質な成果を得やすくなります。
しかし、自社独自のノウハウや文化を反映することが成果物に直結する場合は、社内で進める方がブランドの一貫性や独自性を確保できます。
求めるのが「専門性」なのか「独自性」なのかを明確にすることが重要です。
④ 社内の人員や時間リソースに余裕はあるか
人材や時間が不足している状況では、外部に任せることで負担を分散できます。
反対に、十分な人員と時間を確保でき教育や育成を行う余裕がある場合は、自社で進めることで組織力を高められます。
現状の体制を見極め、リソースに余裕があるかどうかを冷静に判断することが求められます。
外注に向いているケース
外注は「短期間で成果を出したい」「専門性をすぐに取り入れたい」といった場面で特に効果を発揮します。以下のようなケースでは、外注を選ぶメリットが大きくなります。
① 一時的なプロジェクトを進めたいとき
短期間だけ必要となる業務や季節的・イベント的な案件では、外注を活用することが有効です。
新商品のキャンペーン用サイトの制作や、期間限定イベントの広告デザイン・PR活動、さらには年度末の繁忙期に集中する事務作業などが代表例といえます。
このような一度きりの仕事に人材を採用・育成するのは非効率であり、外注を利用する方がコストと時間の両面で節約につながります。
② 高度な専門知識が必要な業務があるとき
社内にノウハウが不足している分野や専門性の高い業務では、外注の力を借りるのが最適です。
たとえばITシステム開発やセキュリティ対策、SEOやWeb広告運用といったマーケティング業務、さらには法務・会計・翻訳などの専門分野が挙げられます。
外注を活用することで高い品質を短期間で確保でき、失敗のリスクを大幅に減らすことが可能になります。
③ とにかくスピードを優先したいとき
急な案件や短納期の仕事では、外注を利用することで必要なリソースをすぐに確保することができます。
短期間で成果物を仕上げなければならない場合や、新規事業の立ち上げで社内の人員だけでは対応しきれない場合、さらにトレンドに即応するマーケティング施策が求められる場面などがその代表例です。
スピードを最優先する状況では、自社での育成や調整を待つよりも、外注を活用する方が高い実行力を発揮できます。す。
内製に向いているケース
内製は「長期的に組織力を高めたい」「情報管理を徹底したい」といった場面で効果を発揮します。以下のようなケースでは、内製を選ぶメリットが大きくなります。
① 継続的に発生する業務を効率化したいとき
定期的に繰り返し発生する業務は、外注に頼るよりも内製で行う方が効率的です。
たとえばWebサイトの更新や運用管理、定常的なデータ分析やレポート作成、さらには社内で常に必要とされるデザイン制作やコンテンツ発信などがその代表例です。
こうした業務を毎回外注するとコストがかさみますが、内製化すれば長期的には人件費だけで運用できるため、コスト効率が高くなります。
② 社内にノウハウを蓄積していきたいとき
企業の競争力を高めるためには、知識や技術を社内に残し蓄積していくことが欠かせません。
自社独自のマーケティング戦略やブランド構築、製品やサービスに直結する研究開発や技術力の強化、さらには社員のスキル成長を通じて次世代のリーダーを育てることが求められます。
外注では得られない「自社にしかない強み」を育てるには、内製による取り組みが必要不可欠です。
③ 機密性が高い情報を扱うとき
顧客データや経営戦略といった外部に漏れると大きなリスクになる業務は、内製で行う方が安心です。
個人情報を含む顧客管理や分析業務、機密度の高い研究開発や技術情報の取り扱い、そして経営戦略や内部文書の作成や管理などがその代表例です。
情報漏えいのリスクを最小限に抑えるためには、外注に頼るよりも内製化によって社内で完結させる方が適しています。
外注と内製を組み合わせる方法

外注と内製は「どちらか一方を選ぶ」ものではなく、状況に応じて使い分けることで最も効果を発揮します。ここでは、両者をバランスよく組み合わせる代表的な方法を紹介します。
方法①|コア業務は内製、スポット業務は外注で分ける
自社の強みや競争力に直結する業務は内製化し、それ以外の一時的または補助的な業務は外注で対応する方法があります。
たとえば自社ブランドに関わる企画や戦略は社内で担当し、デザインや翻訳、短期イベントに関する業務は外部に任せるといった分け方です。
こうすることで長期的なノウハウの蓄積と、短期的な効率化を同時に実現できる点が大きなメリットとなります。
方法②|プロジェクト開始時は外注し、安定後は内製に移行する
新規事業や新しい取り組みでは、立ち上げ時に外注を活用してスピードを優先し、仕組みが安定してから内製化へ移行する方法があります。
初期段階では専門家に任せることでリスクを最小限に抑えつつ、進行の中でノウハウを吸収し、徐々に社内に業務を取り込んでいく流れです。
成長フェーズに応じて柔軟に体制を構築できる点が、この方法の大きな強みとなります。
方法③|内製チーム+外部パートナーでのハイブリッドで行う
社内チームを中心に据えながら、外注先を「協力パートナー」として組み込む方法も効果的です。
基本的な業務は社内で実行しつつ、専門性が求められる部分だけを外部に任せることで、双方の強みを活かすことができます。
外注先とは長期的な関係を築き、セカンドチームのように機能させることで、社内外の力を掛け合わせて高い成果を目指すことが可能になります。
判断に迷ったときのチェックリスト

外注か内製かで迷ったときは、以下のチェック項目を確認すると整理しやすくなります。単にコストだけでなく、品質やリスク管理など多面的に判断することが重要です。
目的はコスト削減?品質アップ?スピード?
まず「何のために外注または内製を選ぶのか」という目的を明確にすることが欠かせません。
コスト削減を優先するのであれば、短期的な案件では外注を利用することで人件費や教育費を抑えられるケースが多くなります。
品質の向上を狙う場合は専門家に任せることで高い完成度を確保しやすく、スピードを重視するなら外注で即戦力を導入できますが、継続的な改善には内製の方が柔軟に対応できます。
社内に人材やノウハウはあるか?
次に確認すべきは、現在の社内リソースです。
すでに必要なスキルを持つ社員がいる場合には、内製を選ぶことで人材の成長と組織力の強化につなげることができます。
一方でノウハウが不足している場合には外注でプロから学び、将来的に内製化を見据えるのも有効ですが、人材不足の状態で無理に内製化を進めると品質や効率が落ち、かえってコスト増につながる恐れもあります。
長期的に考えてどちらが効率的か?
短期と長期では、コストや効果の見え方が大きく異なります。
スポット的な業務やキャンペーン対応といった短期的な案件であれば外注が効率的ですが、長期的に繰り返し発生する業務であれば、社内に仕組みを整えて内製化することでコスト削減とノウハウの蓄積が可能になります。
また、自社の成長戦略と照らし合わせ、どちらが将来的な競争力につながるかを考えることが重要であり、一時的な判断ではなく中長期の経営戦略に沿って選ぶことが失敗を防ぐ鍵となります。
情報管理の観点から問題はないか?
外注においては「情報の扱い」が大きなリスクとなります。
個人情報や顧客データを扱う場合には、外注先のセキュリティ体制を必ず確認することが求められ、契約においても秘密保持契約(NDA)やデータの取り扱い範囲を明文化しておくことが不可欠です。
特に研究開発や経営戦略といった機密性の高い領域については、外注せずに内製化して社内で完結させる方が安心といえます。
まとめ

外注と内製には、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。外注は専門性やスピードに強みがある一方、ノウハウが残りにくいという課題を抱えます。逆に内製はノウハウの蓄積や柔軟な対応に適していますが、人材育成やコスト面での負担が大きくなる傾向があります。
重要なのは「どちらが優れているか」を一律に決めることではなく、自社の状況や目的に応じて比較の軸を明確にすることです。
さらに、外注と内製を完全に二分して考える必要はありません。コア業務は内製しつつ、スポット業務は外注する、立ち上げ期は外注でスピードを優先し、安定後に内製へ移行するなど、組み合わせることで双方の強みを活かすことが可能です。
外注と内製のバランスをうまくとることが、効率的かつ持続的な組織運営につながります。
『運用を始める前のチェックリスト』2大特典無料配布中

CONTACT US
お問い合わせ
マネタイズ顧問や、広告代理、投稿作成代行事業など
お気軽にご相談ください。
お見積もり依頼も可能です。